
こんにちは 今回はこれからの季節に増えてくる「食中毒」についてお話します。「ちゃんと火を通していれば大丈夫」「夏だけ気をつければいいのでは?そんな風に思っている方も多いのではないでしょうか?
梅雨の時期は湿気と気温が高くなるため、細菌性の食中毒が発生しやすくなります。今回はみなさんも一度は耳にしたことがある食中毒の菌の名前だと思います。主な原因や予防のポイントをわかりやすくご紹介いたします。
① カンピロバクター
生あるいは加熱があまりされていない鶏肉(鶏刺し、タタキなど)加熱不十分な鶏肉(バーベキュー、鶏鍋、焼き鳥など)あるいは鶏肉から調理過程の不備で二次汚染された食品などです。
②サルモネラ菌
卵、鶏肉、豚肉、牛肉などの食肉、そしてそれらを原材料とした加工食品。特に、加熱不足の卵料理や、生の鶏肉、レバ刺しなどです。
③黄色ブドウ球菌
この菌は人の皮膚、鼻や口の中、傷口、髪の毛などにいるので、加熱後に手作業を行う食品が原因になります。具体的には、おにぎり、いなり寿司、巻き寿司、弁当、調理パンです。菌は熱に弱いですが、菌が作る毒素は熱に強いので一度毒素ができてしまうと、加熱しても食中毒は防げません。直接食材を触る際は手洗を徹底し、ラップを使っておにぎりなどを握る工夫をしてください。
④ウェルシュ菌
特に肉や、魚介類、野菜を使った煮込み料理、カレー、シチュー、スープなどがあげられます。これらの食品は、大量に調理された後、室温で長時間放置されることで、ウェルシュ菌が増殖しやすくなります。余った食材は小分けにして冷蔵庫に入れるようにしてください。

梅雨時の食中毒対策のポイント
食中毒の予防3原則
・つけない 手洗を徹底し調理器具を清潔に保ち、食材に菌をつけないようにする。
・増やさない 食材の温度管理を徹底し、菌を増やさないようにする。調理後は速やかに冷蔵庫に入れる。
または冷凍する。
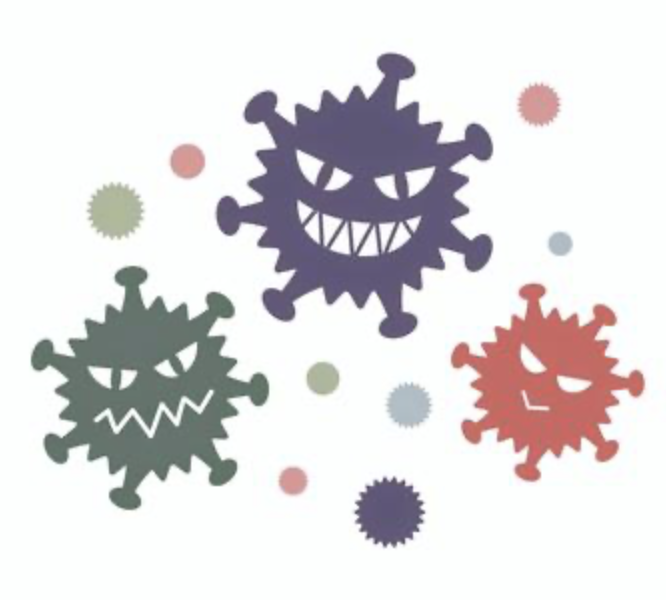
・やっつける 食材は中心部までしっかりと加熱し、菌を死滅させる。
飲みかけのペットボトルには黄色ブドウ球菌が付着しやすく、高湿度な環境に放置すると食中毒のリスクが高くなります。短時間で飲みきれないときは、冷蔵庫で保管するようにしてくださいね。